金属の中でも特に強度としなやかさに優れるチタンは、私たちの生活の様々な場面で活用されています。しかし、その性質の根源である原子レベルの構造、特にチタンの電子配置や、安定した状態であるチタンイオンの電子配置がどのようになっているのか、疑問に思ったことはありませんか。原子の構造を理解するためには、電子配列の基本的なルールを知る必要があります。
この記事では、原子番号22の元素であるチタンを題材に、電子がどのように配置されているのかを基礎から丁寧に解説します。電子殻の構造を示すK殻、L殻、M殻の役割や、さらに詳細な分類であるs軌道、p軌道、d軌道への電子の入り方について学びます。また、電子配置の基本原理である構成原理、電子スピンに関するパウリの排他原理、そして軌道への電子配置を決めるフントの規則という3つの重要なルールについても分かりやすく説明します。さらに、チタン原子が電子を失いイオン化する際の最外殻電子の役割や、チタン原子が持つ価電子数、そして化合物中での状態を示す酸化数についても掘り下げ、安定しやすいチタンイオン電子配置の仕組みを解き明かしていきます。
- チタンの基本的な電子配置の仕組み
- 電子配列を決定づける3つの重要な原理
- チタンがイオンになる際の電子の変化
- 価電子や酸化数と電子配置の深い関係性
チタン電子配置の基礎となる電子配列のルール
- チタンの基本情報である原子番号22
- 電子殻の構造を示すK殻 L殻 M殻
- s軌道 p軌道 d軌道への電子の入り方
- 電子配置の基本原理である構成原理
- 電子スピンに関するパウリの排他原理
- 軌道への電子配置を決めるフントの規則
チタンの基本情報である原子番号22

まず、チタン(元素記号: Ti)という元素の最も基本的な情報から見ていきましょう。 チタンは原子番号22の元素です。 この原子番号は、原子の中心にある原子核に含まれる陽子の数を表しています。そして、原子が電気的に中性である場合、陽子の数と同じ数の電子が原子核の周りに存在します。つまり、チタン原子は22個の陽子と、その周りを飛び交う22個の電子を持っている、ということになります。
この22個の電子が、原子核の周りにどのように配置されているのか、その「住所」のようなものを示すのが電子配置です。 電子配置を理解することは、チタンがなぜ軽くて強いのか、なぜ錆びにくいのかといった化学的な性質を理解するための第一歩となります。
補足:周期表におけるチタンの位置
チタンは周期表において第4周期、第4族に位置する遷移元素の一つです。 周期表の位置は、その元素の電子配置と密接な関係があり、似たような性質を持つ元素が縦の列(族)に並ぶようにできています。チタンが遷移元素に分類される理由は、後述するd軌道に電子が満たされていない(不完全なd殻を持つ)ことに由来します。
電子殻の構造を示すK殻 L殻 M殻
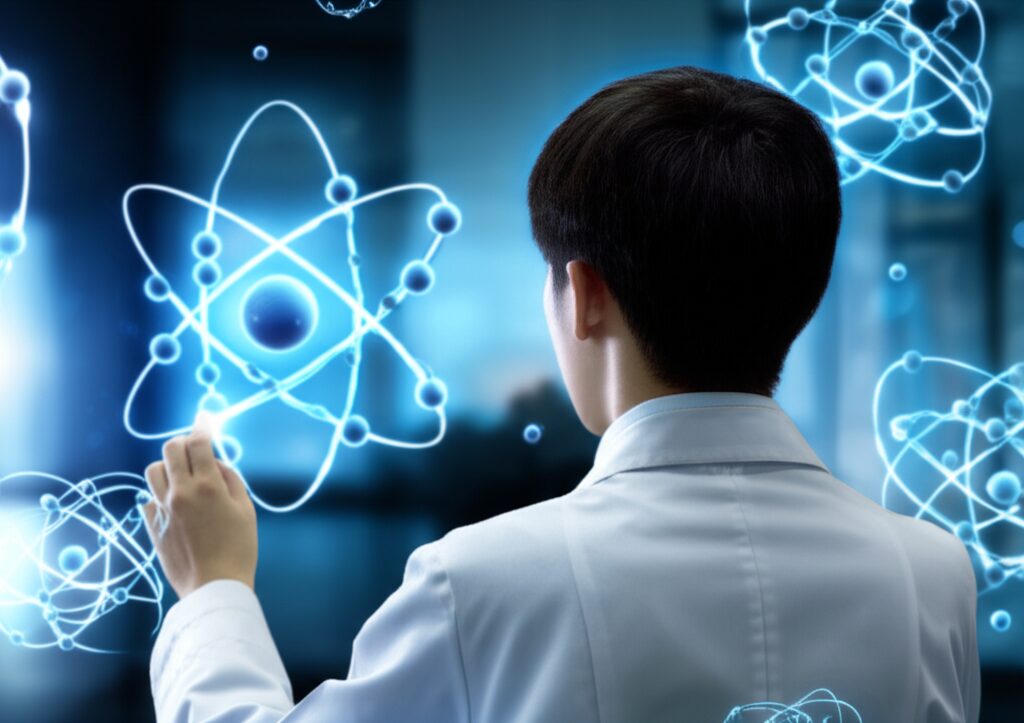
原子核の周りに存在する22個の電子は、無秩序に飛び回っているわけではありません。実は、電子は原子核を中心としたいくつかの層に分かれて存在しており、この層のことを電子殻と呼びます。 電子殻は、エネルギー準位が低い、つまり原子核に近い内側から順にK殻、L殻、M殻、N殻…とアルファベットで名付けられています。
それぞれの電子殻には、収容できる電子の最大数が決まっています。 内側からn番目の電子殻に収容できる電子の最大数は「2n²」という簡単な式で計算できます。
| 電子殻 | 主量子数 (n) | 最大収容電子数 (2n²) |
|---|---|---|
| K殻 | 1 | 2 × 1² = 2個 |
| L殻 | 2 | 2 × 2² = 8個 |
| M殻 | 3 | 2 × 3² = 18個 |
| N殻 | 4 | 2 × 4² = 32個 |
チタンの持つ22個の電子は、このルールに従って内側のK殻から順番に埋まっていきます。 具体的には、K殻に2個、L殻に8個、M殻に10個、そしてN殻に2個の電子が入るという配置になります。 これがチタンの電子配置の基本的な骨格です。
「なぜM殻は最大18個まで入れるのに、10個しか入っていないの?」と疑問に思うかもしれません。実は、電子殻はさらに細かい部屋に分かれており、その部屋に入る順番が少しトリッキーなのです。次のs軌道、p軌道、d軌道で詳しく見ていきましょう。
s軌道 p軌道 d軌道への電子の入り方

前述のK殻、L殻、M殻といった電子殻は、実はさらに細分化された電子軌道(または原子軌道)というグループで構成されています。 この電子軌道には形状によって種類があり、それぞれs軌道、p軌道、d軌道、f軌道…と名付けられています。
- s軌道: 球形の軌道が1種類あります。
- p軌道: 亜鈴(ダンベル)のような形をした軌道が、x, y, zの3つの異なる方向を向いて3種類存在します。
- d軌道: さらに複雑な形をした軌道が5種類存在します。
そして、どの種類の軌道であっても、1つの軌道には最大で2個までしか電子を収容できません。 このルールから、各軌道グループ全体で収容できる電子の最大数が決まります。
各軌道グループの最大収容電子数
- s軌道:1種類 × 2個 = 2個
- p軌道:3種類 × 2個 = 6個
- d軌道:5種類 × 2個 = 10個
電子殻と電子軌道の関係は以下のようになっています。
- K殻(n=1): 1s軌道のみ
- L殻(n=2): 2s軌道と2p軌道
- M殻(n=3): 3s軌道、3p軌道、3d軌道
- N殻(n=4): 4s軌道、4p軌道、4d軌道、4f軌道
電子は、これらの軌道のうちエネルギー準位が低いものから順番に埋まっていきます。 ここで重要なのは、必ずしもM殻の軌道が全て埋まってからN殻の軌道が埋まるわけではない、ということです。実は、エネルギー準位は3d軌道よりも4s軌道の方が少し低いため、電子は3p軌道が埋まった後、3d軌道よりも先に4s軌道に入ります。 これが、先ほどの「M殻が満杯になる前にN殻に電子が入る」理由です。
電子配置の基本原理である構成原理
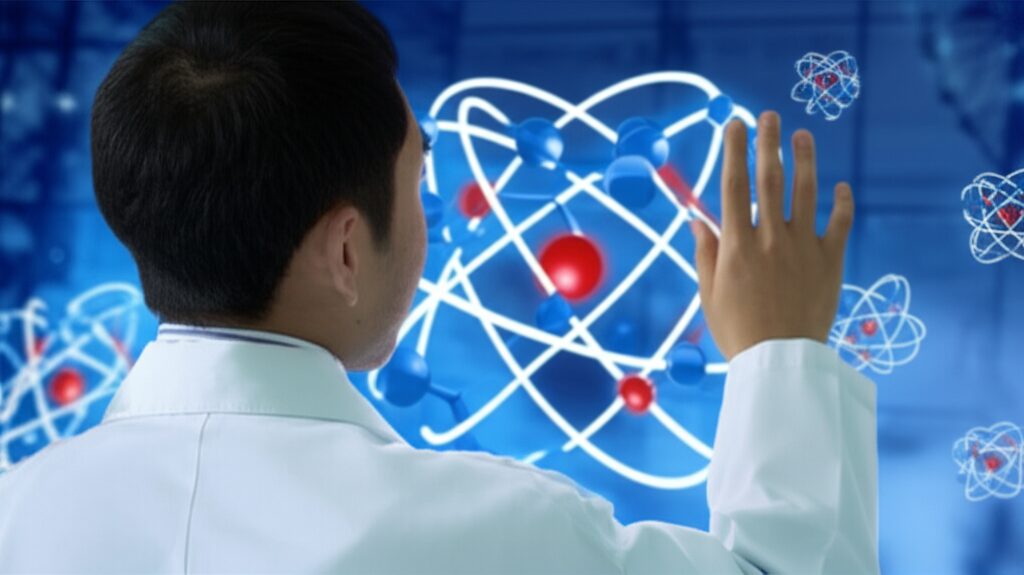
原子の電子配置は、気まぐれに決まるわけではなく、3つの重要な基本原理に従っています。その1つ目が構成原理(または積み上げ原理)です。
構成原理とは、電子は利用可能な軌道のうち、最もエネルギー準位の低い軌道から順番に収容されていくという、非常にシンプルなルールです。 原子全体が最も安定した状態(基底状態)になるためには、電子ができるだけ原子核の近く、つまりエネルギーの低い位置にいる方が都合が良いためです。
軌道のエネルギー準位は、おおよそ以下の順番で高くなっていきます。
1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p …
注意:4s軌道と3d軌道の逆転
ここで改めて注目すべきは、3p軌道の次に電子が入るのは3d軌道ではなく、4s軌道であるという点です。 これは、軌道のエネルギー準位が単純に電子殻の順番(K→L→M)だけでは決まらないことを示しています。このエネルギー準位の逆転が、チタンのような遷移元素の化学的性質を理解する上で非常に重要なポイントとなります。
この構成原理に従って、チタンの22個の電子をエネルギーの低い軌道から順に配置していくと、以下のようになります。
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d²
これは、アルゴン(Ar)の電子配置 [Ar] を使って、より簡潔に [Ar] 3d² 4s² と表記されることもあります。 これがチタン原子の基底状態における電子配置です。
電子スピンに関するパウリの排他原理

電子配置を決める2つ目のルールが、パウリの排他原理(排他律とも呼ばれます)です。
この原理を理解するためには、まず「電子スピン」という概念を知る必要があります。電子は、地球が自転しているように、それ自体がスピン(自転)していると考えることができます。このスピンには「上向き(↑)」と「下向き(↓)」の2つの状態があります。
そして、パウリの排他原理とは、「1つの原子軌道には、互いに逆向きのスピンを持つ電子が最大で2個までしか入ることができない」というルールです。
パウリの排他原理の要点
- 1つの軌道(部屋)に入れる電子は2つまで。
- その2つの電子は、必ず異なるスピン(上向き↑と下向き↓)を持たなければならない。
- 同じ向きのスピン(例:上向き↑と上向き↑)を持つ2つの電子が、同じ軌道に入ることは許されない。
この原理があるからこそ、s軌道には2個、p軌道には6個、d軌道には10個という最大収容電子数が決まるのです。もしこのルールがなければ、全ての電子が最もエネルギーの低い1s軌道に集中してしまい、現在のような多様な元素や化合物は存在しなかったでしょう。パウリの排他原理は、原子の構造と物質の多様性を支える根源的な法則の一つと言えます。
軌道への電子配置を決めるフントの規則
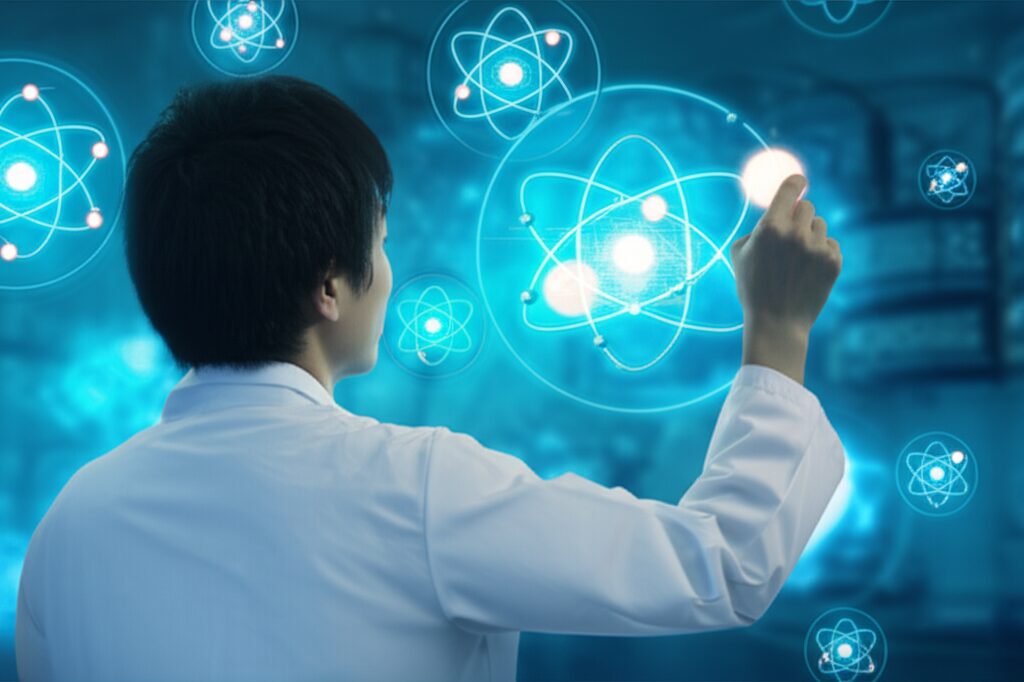
電子配置の最後の仕上げとなる3つ目のルールが、フントの規則です。
この規則は、p軌道やd軌道のように、同じエネルギー準位を持つ軌道が複数存在する(これを「縮重している」と言います)場合に適用されます。フントの規則とは、「同じエネルギー準位の軌道に電子が入るとき、可能な限りスピンが平行(同じ向き)になるように、別々の軌道に1つずつ配置されていく」というものです。
これは、バスの座席に例えると分かりやすいかもしれません。同じ列に空いている席がたくさんある場合、わざわざ他の人の隣に座るよりも、まずは誰も座っていない席に1人ずつ座っていきますよね。電子も同様に、同じエネルギーの軌道(座席)が複数あれば、まずは1つずつ別々の軌道を占有しようとします。電子同士は負の電荷を持っていて反発し合うため、できるだけ離れていた方が安定するためです。
チタンの電子配置 [Ar] 3d² 4s² を例に考えてみましょう。 最も外側の電子は3d軌道に入ります。3d軌道はエネルギー準位が同じ5つの軌道から成り立っています。ここに2つの電子が入る場合、フントの規則に従って、2つの電子は別々の3d軌道に、同じ向きのスピン(例えば上向き↑)を持って配置されます。
このように、構成原理、パウリの排他原理、そしてフントの規則という3つのルールを組み合わせることで、あらゆる原子の正確な電子配置を決定することができるのです。 チタンの場合は、これらのルールによって[Ar] 3d² 4s²というユニークな電子配置が形成され、それがチタン特有の性質を生み出しています。
安定しやすいチタンイオン電子配置の仕組み
- イオン化に関わる最外殻電子の役割
- チタン原子が持つ価電子数について
- 化合物中での状態を示す酸化数
イオン化に関わる最外殻電子の役割
原子は、他の原子と化学結合を作る際に、電子を失ったり、あるいは受け取ったりすることがあります。このようにして電荷を帯びた原子のことをイオンと呼びます。このイオン化のプロセスにおいて中心的な役割を果たすのが、最外殻電子です。
最外殻電子とは、その名の通り、原子の最も外側にある電子殻に存在する電子のことを指します。 最も外側にいるため、原子核からの束縛が相対的に弱く、化学反応の際に最も動きやすい電子となります。
チタンの電子配置は [Ar] 3d² 4s² でした。この表記を見ると、最も大きな主量子数を持つ電子殻はN殻(n=4)です。したがって、チタン原子の最外殻はN殻であり、そこに含まれる4s軌道の2つの電子が最外殻電子となります。
注意:電子を失う順番
電子配置を決めるとき(構成原理)は、エネルギー準位の低い4s軌道に先に電子が入りました。しかし、原子が電子を失って陽イオンになるときは、エネルギー準位の順番ではなく、単純に最も外側の電子殻から電子が失われます。チタンの場合、最も外側はN殻(4s軌道)なので、イオン化する際にはまず4s軌道の電子から失われるという点が非常に重要です。
チタン原子が持つ価電子数について
最外殻電子と非常によく似た概念に価電子があります。価電子とは、原子が他の原子と化学結合を形成する際に役割を果たす電子のことです。 ほとんどの典型元素では、「最外殻電子の数 = 価電子の数」となりますが、チタンのような遷移元素では少し事情が異なります。
遷移元素の場合、最外殻電子だけでなく、その一つ内側の電子殻にあるd軌道の電子も化学結合に関与することがあります。 チタンの電子配置 [Ar] 3d² 4s² を見ると、最外殻電子は4s軌道の2個です。しかし、化学反応の条件によっては、その内側にある3d軌道の2個の電子も結合に使われることがあります。
このため、チタンの価電子数は状況に応じて変化し、これが次に説明する「複数の酸化数を取る」という遷移元素特有の性質につながります。一般的に、チタンの価電子数は、最外殻の4s電子と3d電子を合わせた4個と見なされることが多いです。
最外殻電子と価電子の違いのまとめ
- 最外殻電子:最も外側の電子殻にある電子の「数」。物理的な位置に基づきます。
- 価電子:化学結合に関与する電子の「数」。化学的な役割に基づきます。
- 典型元素:多くの場合、最外殻電子数と価電子数は一致します。
- 遷移元素(チタンなど):最外殻電子(例:4s電子)と、内側のd軌道電子(例:3d電子)が共に価電子として振る舞うことがあります。
化合物中での状態を示す酸化数
酸化数とは、化合物の中で、その原子がどれくらい電子を失ったか(または得たか)を仮想的に表す数値です。イオンの価数と似ていますが、共有結合している化合物など、イオンになっていない場合にも使われる便利な指標です。
チタンは価電子として振る舞うことができる電子を複数持つため、+2, +3, +4 といった複数の酸化数を取ることができます。 これはチタンが形成するイオンの種類に対応しています。
チタンが取る主な酸化数とイオンの電子配置
チタンがイオンになるときは、前述の通り最も外側の4s軌道から電子を失います。
- 酸化数+2 (Ti²⁺): 4s軌道から電子を2個失います。電子配置は [Ar] 3d² となります。
- 酸化数+3 (Ti³⁺): 4s軌道から2個、3d軌道から1個の電子を失います。電子配置は [Ar] 3d¹ となります。
- 酸化数+4 (Ti⁴⁺): 4s軌道から2個、3d軌道から2個、つまり価電子を全て失います。電子配置は [Ar] となり、安定な貴ガスであるアルゴンと同じ電子配置になります。
この中で、最も安定な酸化数は+4です。 これは、Ti⁴⁺イオンが貴ガスと同じ安定した閉殻構造をとるためです。 日常で目にするチタン化合物の多く、例えば白色顔料として使われる酸化チタン(IV) (TiO₂) などでは、チタンはこの+4の酸化数を取っています。
| 状態 | 酸化数 | 電子配置 | 失われる電子 | 安定性 |
|---|---|---|---|---|
| チタン原子 (Ti) | 0 | [Ar] 3d² 4s² | – | – |
| チタン(II)イオン (Ti²⁺) | +2 | [Ar] 3d² | 4sから2個 | 比較的安定 |
| チタン(III)イオン (Ti³⁺) | +3 | [Ar] 3d¹ | 4sから2個, 3dから1個 | 不安定(酸化されやすい) |
| チタン(IV)イオン (Ti⁴⁺) | +4 | [Ar] | 4sから2個, 3dから2個 | 最も安定 |
このように、チタンの電子配置、特に価電子の振る舞いを理解することで、なぜチタンが多様な化合物を形成し、その中でどの状態が最も安定するのかを論理的に説明することができるのです。
まとめ:チタン電子配置とチタンイオン電子配列
- チタンの原子番号は22で22個の電子を持つ
- 電子は原子核の周りを層状に存在する電子殻に収容される
- 電子殻は内側からK殻 L殻 M殻 N殻と呼ばれる
- 各電子殻はさらにs軌道 p軌道 d軌道などの電子軌道に分かれる
- 電子配置は基本的に3つのルールによって決まる
- 構成原理はエネルギー準位の低い軌道から電子が埋まるというルール
- パウリの排他原理は1つの軌道にスピンが逆の電子2個までしか入れないルール
- フントの規則は同じエネルギーの軌道にはまず平行スピンで1つずつ入るルール
- これらのルールに従うとチタンの電子配置は[Ar] 3d² 4s²となる
- 原子がイオンになる際は最も外側の電子殻にある最外殻電子から失われる
- チタンの場合、4s軌道の電子が最外殻電子でありイオン化の際に先に失われる
- 化学結合に関わる価電子はチタンの場合4sと3dの電子が相当する
- チタンは+2 +3 +4など複数の酸化数を取ることができる
- 酸化数+4のチタンイオン(Ti⁴⁺)は貴ガスのアルゴンと同じ電子配置[Ar]となり最も安定する
- チタンイオンの電子配列を理解することはチタン化合物の性質を予測する上で重要である
